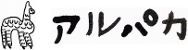本屋さんのつぶやき日記 第4回 「他人の人生を生きるということ」 すずとも店長
小説をそれほど読まない。ただ自分にとってなにか困難なことが起きた時に、小説が目の前に現れてくる気がしている。
私にとってはいつも音楽の方が親しかった。ある時はギターを弾くことだったり、バッハを聴くことだったりした。しかし小説を読むことはそれとはまた別の経験だ。他人の傷を感じることで自分の傷を癒やす。小説にはそんな役割もある。
平野啓一郎の小説に出てくる「ある男」は谷口大祐という。ただし、これは本名ではない。大祐は九州の小さな町にやってきて林業の仕事に就く。そこで昔ながらの商店街の文房具屋さんの娘里枝と結婚する。町にやって来た理由は明らかではなかったが、結婚を決意させるほどの信頼のおける人物だった。だが大祐は倒れてきた木の下敷きになり死んでしまう。葬式にやって来た兄は言った。これは誰だ? 私の弟ではない。大祐になりすましたある男Xはいったい何者なのか? それを軸に物語は進む。
妻の里枝は以前離婚していた。その離婚の際の代理人であった城戸弁護士がもう一人の主役である。彼は在日三世だ。生まれた時から日本で暮らし全く普段は意識することはない。しかし話が進むうちその出自がじわじわと彼を苦しめる。それ以外は家庭内不和を抱えていて孤独を感じる普通の中年だ。
ある時、城戸は戯れにバーで谷口大祐の名を名乗る。このシーンは戯れであっても象徴的だ。別人になること。Xにはそうしなければならない理由があった。それが明らかになるにつれ城戸は弁護士の業務の範疇を越えて、Xの人生を知ることにのめり込んでいく。あたかも他人の人生をたどることで自分自身を確かめているような……
その行為は小説家そのものであり、また読者そのものでもある。
ラストは感動的だ。愛にとって過去は必要なのか。いまここにいるその人の存在を確かに認めてあげればそれで良いのではないか。苦悩する男Xがついにたどり着いた場所、そうした家族の物語でもある。
ところで、作者の平野啓一郎はツイッターでも積極的に時事的な発言をしている。立場の違う人間から攻撃対象となるのではないかと心配してしまう。
この「ある男」でもその関心は如何なく発揮されている。在日、ヘイトスピーチ、死刑問題、DV、などの問題を普段考えてみる機会がなくても、リアリティのある描写でこれらの問題について知らず知らずのうちに考えさせられる。
差別することや生きていて感じる様々な違和感などを読み進むうちに自然と受け入れられ、声高に主張するだけではない、「小説」という形式の可能性を改めて感じた。また、作品中でも里枝の息子悠人が弟を亡くし、実父、義父と別れた痛みに「文学が…救いになってい」た。
生まれながらに持った資質を抱えて生きるとはどういうことか…登場人物、我々、それぞれの重みは違っても、誰もがこの「ある男」と同じものを抱えて生きている。
とりあげた本
平野啓一郎 『ある男』文藝春秋/2018年

執筆者プロフィール

-
すずとも店長/地方都市・某大手書店の店長。ウィスパーボイスで基本マイペース。
テンションに波がない安定したひと、と思いきや、意外に涙もろい(書店勤務L・談)